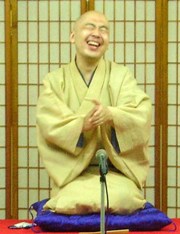志雲 談坊兄さん(※3)もいてたし、家元からは「米朝師匠(※4)の形がきちんとしているから、それで覚えろ。きちんと覚えてきたら見てやる」て言われました。米朝師匠は音源、活字がたくさんありますから、それらを参考に覚えて、移動の車の中で見てもらったこともありましたよ。
そのころの家元の移動車、ものすごい年代もんのワゴンでしたんやわ。どっかから払い下げてもろて来たような。当時「日本すみずみ出前寄席」(※5)いうのをやってて、それを大きな寄席文字でね、紺色の車体に白いペンキで書いてあるもんやさかい、よう右翼の街宣車と間違えられました。
――初高座はいつごろですか?
志雲 89年の夏ごろには高座に出してもろてたと思います。あまり正確には覚えてませんが。
――高座名は師匠がつけてくれたんですか?
志雲 候補4つから選べと。志雲の「雲」はね、三国志の雲長(※6)か、趙雲(※7)かどっちか。うちの師匠、三国志好きやから。ほかの3つは談平(※8)、志林、志麟。
――入門当時、前座の先輩にはどんな方がいましたか?
志雲 志らく兄さんまではもう二つ目で、前座は何人かおったのですが、すぐ辞めたりして、実質は生志兄さん(※9)と僕と、生志兄貴より1年ぐらい先輩の人と3人でした。
この先輩という人は某新興宗教の信者で、後にわかったことですが、そこの教義を広めるため話術を磨こうと、噺家になった人やったんです。後輩がこんなん言うのなんやけど、ほ〜んまに個性的な語り口やったんですよ。およそね、人前でしゃべって落語として評価される感じやなかった。その人の友達やったら1回目は聴きに行くけど、2回目は行かへんやろ、みたいな。でも、不思議なことにその人、仕事はあるんですよ。落語の仕事だけやなかったとは思いますけど。あれも資質ですかね、宗教がらみだけやなしに、どこへでも入っていこうという積極性もあったんでしょうな。その人、二つ目に昇進したとき「おれは人間関係だけで二つ目になった」て自分でも言うてはって。「やれ落
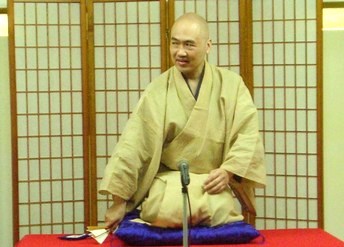 語が上手いじゃの、下手じゃの、芸があるのないの、てなことは仕事の量にはあんまり関係ないんやな」て、そのときは思いましたねえ。不思議な人でしたよ、いやほんまに。
語が上手いじゃの、下手じゃの、芸があるのないの、てなことは仕事の量にはあんまり関係ないんやな」て、そのときは思いましたねえ。不思議な人でしたよ、いやほんまに。――文都さんや談春さんのように、築地にぶち込まれたりしなかったんですか?(※10)
志雲 僕は築地やのうて、家元の行きつけの「美弥」って銀座のバーね。長いことやってたバーテンさんが辞めてしもて困ってるから「おまえ行って来い」と。蝶ネクタイ締めてバーテンやりましたで。昼間は師匠のかばん持ちしながら、半年ぐらい。
――文都さんから稽古をつけてもらったことはありますか?
志雲 ありますよ。文都兄さんにも、ずいぶん世話になりました。それこそ一番基本の「つる」いう噺がありますけど、米團治師匠(※11)がつくらはったらしい台本みたいな資料もろたりね。演出的な細かいこともちゃんと書いてある有難い資料です。「つる」は噺自体も面白いですけどね、米朝師匠も言うてはるように、落語のテクニックとか、かなり入っているから、これをきっちりマスターしたら、いろいろ身に着くし、けっこう応用が利くんです。
――立川流以外の師匠に稽古をつけてもらったことは?
志雲 鶴光師匠(笑福亭、2代目)と、大阪の福笑師匠(笑福亭)に稽古つけていただいたことがあります。鶴光師匠は仕事をご一緒させていただいたときお願いしたら、ご快諾いただいて「牛ほめ」をつけてもらいました。大阪では「池田の牛ほめ」言うてますけど。